また、先生が擬人化してエロい事してますのでその点も
問題ない方はハートをクリックしてください
このSSは、2011年5月発売のLaLa本誌扉絵について友達との間で物議を醸したことが
きっかけて書いてくれました(笑)
まあ、エロ絵描くことが条件だったんですけど(笑)
掲載イラストを見ていないと分かりにくいかもしれないので一応関連日記にリンクはりました。
2011.9時点でコミックス未収録部分の感想に触れているのでOKな方だけこちらをご参照ください★
P.S.お友達は本来エロ作家ではありません(笑)
当人、本業ジャンルよりも夏目でエロ書いてる!!という事に気がつき悶絶してました・・・(笑)
★そんなお友達から、本文と一緒に添えらてきたコメント★
「ウチのパソコン、「きょうせい」って打つと、「強制」でなく「嬌声」って答えるエロい子になってしまいました。」
夏目のために?もっと卑猥な子(PC)に育て上げて下さい、敬礼!(笑)
#1
■全部、夏の暑さが悪いんだ!■
もしかして、もう夏が来たのだろうか。
夏目は頭上の日を仰ぎ見ながらそう思った。
風は爽やかだが、日を遮るもののない路地を片手に重い荷物を下げて歩くと少々汗ばむ。
「おい、それはなんだ?」
誰もいない路地で不意に声がかかる。
そちらに顔を向けなくとも、夏目にはその正体は分かった。ニャンコ先生だ。
部屋にいなかったからどこかに出掛けたのだろうと思っていたが、こんなところまで来ていたらしい。
部屋にいなかったからどこかに出掛けたのだろうと思っていたが、こんなところまで来ていたらしい。
ブロック塀の上から肩に飛び乗ったニャンコ先生を、夏目は横目で睨んだ。
「見ての通りのスイカだよ。これ重いんだから、そっちの肩に乗らないでくれよ」


ニャンコ先生は慣れたもので、澄ました顔で反対の肩に移った。
「随分と大きなスイカではないか。甘そうだな。
まんじゅうも好きだがたまにはこういうのも悪くない。
夏目、早く食わせろ」
まんじゅうも好きだがたまにはこういうのも悪くない。
夏目、早く食わせろ」
「駄目だよ、これは塔子さんが貰ったものなんだから。俺は代理で受け取りにいっただけだ」
ご近所の夫婦が趣味で作っている家庭菜園に今年初もののスイカが実ったとかで、
藤原家もそのお裾分けを頂くことになった。
ただ夫婦ともに高齢で持って行くのは辛いとのことで、学校から帰ったばかりの夏目が
それを受け取りに行ったのだ。
藤原家もそのお裾分けを頂くことになった。
ただ夫婦ともに高齢で持って行くのは辛いとのことで、学校から帰ったばかりの夏目が
それを受け取りに行ったのだ。
趣味で作ったとは思えないような立派なスイカはそれだけ大きく、そして重かった。
「…お前、汗の匂いがするな」


ニャンコ先生が夏目の首筋に鼻先をつける。
「暑いんだから、当然だろ?」
肩に重みがかかったせいで、先ほどまでより暑く感じる。
「…近道、していくか」
細いわき道から林を抜けていくと、藤原家までの近道になる。
細い川沿いの道は木陰にもなっているから、アスファルトの上を歩くよりずっと涼しい。
ただ、人気がなく妖が好んで使う道だ。
よく知る八ツ原の妖ほど夏目に対して好意的ではない者も多い。
細い川沿いの道は木陰にもなっているから、アスファルトの上を歩くよりずっと涼しい。
ただ、人気がなく妖が好んで使う道だ。
よく知る八ツ原の妖ほど夏目に対して好意的ではない者も多い。
「こりない奴だな、お前」
この道で何度か妖に追いかけられたことを知っているニャンコ先生は、あきれたように言った。
「今日は大丈夫だろ?用心棒が居るんだから」
夏目が先生の柔らかい背中を撫でてそう言うと、ニャンコ先生がふんと鼻を鳴らした。
林の中の道は思ったとおり涼しかったが、上り坂だったのは夏目の計算外だった。
「…涼しい、けど、暑い…」
重い荷物を両肩に持ってでこぼこした土の坂道を登るのは、思ったより体力を使う。
「ほれほれ、もっときりきり歩かんか!」
「先生が肩から降りてくれたら、もっと早く歩けるよ…」
暢気に急かすニャンコ先生を軽く睨んで、夏目はことさらゆっくりと歩いた。
用心棒の効果ではないだろうが、今日は追ってくるような妖はいない。
用心棒の効果ではないだろうが、今日は追ってくるような妖はいない。
坂を上りきると、緩やかな下り坂になった。
「ほら、下り坂なんだから、自分で歩けよ、先生」
促すが、ニャンコ先生はそ知らぬ顔だ。
促すが、ニャンコ先生はそ知らぬ顔だ。
夏目はため息一つで諦めて、坂を下った。
坂を下りきると、その先には川が流れていた。
小川というには流れが早いが、点々と転がる岩が橋の役目を果たしており、道は川の向こうに続いている。
小川というには流れが早いが、点々と転がる岩が橋の役目を果たしており、道は川の向こうに続いている。
「滑って落ちるなよ」
「このくらい平気だよ」
「どうだか、お前はどんくさいからな」
「先生こそ、落ちたことあるんじゃないのか?」
ニャンコ先生がぐっと押し黙る。
酔っ払った挙句に泥だらけになったりびしょ濡れになったりして夜中に帰ってきたことが何度かあるが、その内の一回はここで落ちたのだろう。
酔っ払った挙句に泥だらけになったりびしょ濡れになったりして夜中に帰ってきたことが何度かあるが、その内の一回はここで落ちたのだろう。
「しょうがないな。落ちないようにしっかり捕まってろよ」
低く唸るニャンコ先生に夏目はからかうように言って、岩に一歩を踏み出した。
ひょいひょいと三つ目の岩に足をかけたとき、夏目の首筋を生暖かいものがするりと撫でた。
「う…うわぁっ!」
ぞろりと背筋が寒くなり、夏目は思わず持っていたスイカを手放した。
「な、何するんだよっ、先生!」
正体は分かっている。ニャンコ先生が首筋を舐めたのだ。
「ふん。ワタシを馬鹿にするからだ。それよりいいのか?スイカが流れていくぞ」
「ああっ!大変だっ!」
割れなかったのは幸いだが、プカプカと浮き沈みしながらスイカは早い流れに乗ってドンドンと下っていく。
夏目は大慌てで流れを追いかけた。
しかし、足場は不安定な岩しかなく、川岸は草が繁っており、みるみるとスイカは見えなくなってしまった。
「ど、どうしよう…」
「慌てるな。おそらくこの先の沼に流れ着いてるさ」
「沼があるのか?」
「ああ、着いて来い」
ニャンコ先生はようやく夏目の肩から降りて、林の中の獣道に入っていった。
<next>
#2
身軽なニャンコ先生の後を追って茂みを掻き分けしばらくいくと、沼はすぐに見えてきた。
学校のプールくらいの広さの水面に木々が張り出し、岸には葦が繁っている場所もある。
流れ込む水量に比べ、なぜか流れ出ていく水のほうが遥かに少ない。
「地下水にでもなってるのかな…」
「あの川を下ったものなら、まずここで見つかる」
岸に立ってとりあえず目を凝らしてみるが、スイカらしきものは浮かんでいない。
「その辺の木か葦にでも引っかかっておるのかもしれんぞ。ああ、あの当たりもくさいな」
そう言って、ニャンコ先生は朽木と倒木の重なりあっている当たりを前足で示した。
「どうやって行ったらいいんだ?道は?」
「そんなものは無い」
あるように見えるか、とあっさりと答えられる。
「…先生、見てきてくれよ。沼の真ん中あたりまでいけばぐるりと見渡せるだろうし、スイカも見つかるかもしれない」
「やーなこった。自分で行け」
「沼に入らなきゃならないじゃないか」
「入ればよかろう?ここには危険な妖は棲んではおらん」
手伝う気は全くないらしく、ニャンコ先生はその場に座って落ち着いてしまった。
水面を覗いてみても、あまり深いようには見えない。先生の言うとおり、水は澄んできれいだった。
底の小石や水草や、その合間を泳ぐ魚まではっきりと見える。
「しょうがないな…」
夏目は覚悟を決めた。
靴を脱ぎ制服のズボンの裾を捲り上げて、沼に入る。

水は冷たくて、気持ちよかった。
忘れていた初夏の暑さを夏目は思い出した。
「気持ちいいな。先生も来ない…あれ?」
ニャンコ先生を呼んでやろうと振り返ったが、先ほどまで居たそこにニャンコ先生の姿はなかった。
「先生?おーい、先生ー!」
何度か名前を呼んでも、ニャンコ先生は姿を現さなかった。
飽きっぽいから待っているのに飽きたのかもしれない。
何となく残念に思ったが、あえて探し回るほどのことも感じず、
夏目はニャンコ先生を呼ぶのを止めて沼の真ん中に向かって歩き出した。
ところが、浅かったのは夏目が足を踏み入れた付近だけで、沼は全体として思っていたより深かった。
岸辺は踝程度だった水かさは、一歩足を進めるごとに足首から下肢まで届き、膝まで捲り上げたズボンを濡らした。
もっと奥まで入ったら、制服のズボンはずぶ濡れになる。
いくら天気がよくても、藤原家に帰るまでに乾きはしないだろう。
と言って、スイカを諦めるのも申し訳ない。
夏目は周囲を注意深く見回した。
幸いにして妖の気配はなく、ニャンコ先生もどこかへ姿を消している。
「誰も見てないよな…?」
夏目はくるりと踵を返し岸に上がると、制服のズボンを脱いだ。

どうしても陽に焼けない白い足が顕わになる。
自分の貧弱な体つきがコンプレックスである夏目は、この細くてつるんとした足も好きではなかった。
さっさと隠してしまおうと、夏目は先ほどよりも勢いをつけて沼に入った。
沼の真ん中近くまで進むと、太ももまで水に浸かった。
深い場所はもっと、それこそ腰や肩まで浸かるくらいかもしれないが、さすがに泳ぐつもりは夏目にはない。
深かそうな場所は避けて沼を半周した。
葦の繁みには無かったから、もしあるなら朽木の辺りだろう。
水面まで大きく張り出した木の枝と朽木が重なりあっているところなら、同じ緑色のスイカは見つけにくい。
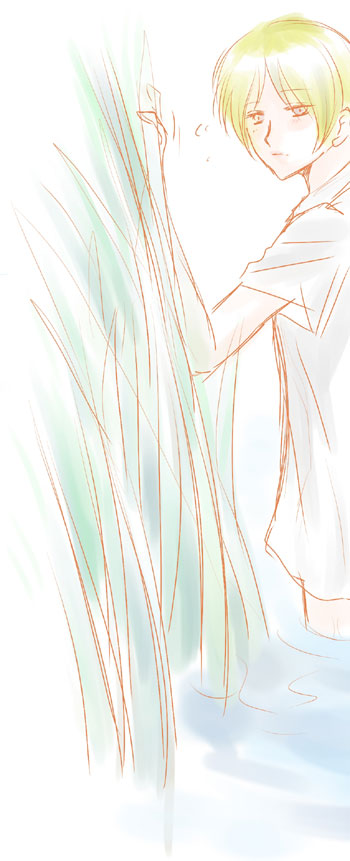
凡その目算をつけたあたりまで、夏目はざぶざぶと水音を立てて進んだ。
自身の立てた水音のせいで、小さな水音が近づいてくることに、夏目は気がつかなかった。
<next>
#3
「ふぁっ!」
突然、生暖かいものが夏目の足の付け根を撫でるように滑った。

ニャンコ先生に舐められたのだと、夏目はすぐに察した。
察することができるほど、その感触を夏目は何度も味わっている。
「いきなり何するんだ、先生!」
水面に浮かんでいるであろうニャンコ先生を探したが、どこにもいない。
「せんせ…っん!」
背後からするりと伸びてきた腕が、夏目のアバラと顎を拘束した。

耳元でくつくつと嗤う声が聞える。
声が違う。
ニャンコ先生の声ではない、若い男の声だ。
そもそも姿が違う。
ニャンコ先生にも、本性である斑にも腕などない。
それでも、これは斑だと、夏目は知っている。
夏目を知り尽くした斑は、妙な薬か呪いでも使われているのではないかと疑いたくなるほど簡単に夏目の身体をを麻痺させた。
しなやかな指先が蠢いているのは頬であるのに、背筋をざわりと何かが突き抜けるのを感じる。
それはすぐに全身に行きわたり、夏の暑さではない熱を夏目に与える。
それはすぐに全身に行きわたり、夏の暑さではない熱を夏目に与える。
あっという間に堕ちる自分の身体が恨めしく、恥ずかしい。
「や…めろ、よ。…せん、せぃ…」
「いやだね」
夏目を捕らえた斑の手が、制服のシャツの隙間から素肌に触れた。
妖は汗をかかないのだろうか、指はひんやりと冷たい。すでに汗ばんでいる夏目の肌とは違う。
「手伝えと言ったのは、お前だろう、夏目?」
「ひゃ…やめ、ん…」
人より長い舌が、夏目の耳を器用に舐めると堪えきれずに嬌声が漏れた。

<next>
#4
夏目が声を出したことに気をよくしたのか、斑の手はさらに好き放題に動き始める。
胸の取っ掛かりをすべらかな掌が刺激し、爪が引っかき、指で摘み上げられた。
思うがままに乱れる自分が憎らしい。
夏目はせめてもの意趣返しにと、声だけは必死で飲み込んだ。息が熱くなるのは仕方がない。
「ここには誰もおらんぞ。声を殺すことはあるまい」
夏目はぶんぶんと首を左右に振る。
斑はさらに興に乗ったようだった。
するり、と下着の中に入り込んできた指が、夏目の性器に絡みつく。
軽く握りこまれただけで、夏目の膝は笑う。
「こらこら、しっかり立たんか。制服を濡らしたくないんだろう?」
口ではそういいつつも、斑は夏目の身体をしっかりと抱え込んで離さない。
半端に開いた唇に、指が差し込まれた。反射的に夏目はその指を舐めしゃぶった。

唾液が、雫となって水面に滴り落ちる。
滴り堕ちているのは唾液だけではなかった。
「夏目、見てみろ」
斑に促されて僅かに顎を引くと、水面にぼんやりと写る自分の姿が見えた。
しかしそれは水面が波打つたびにゆがみ、ただでさえ朦朧とした夏目の目には
沼の底の色と混じりあって、あまり羞恥をあおりはしなかった。
夏目の羞恥を煽ったのは、流れていく白い糸のようなものだった。
口に差し入れられたのとは反対の手は、ずっと夏目の性器を嬲っている。
片手だけで起用に袋を揉み上げ、筋を指の腹で擦り、先端に爪を立てる。
そんなことを続けられれば、慣れた身体だ。夏目は感じずにはいられない。
先走りの液が下着から染み出て水面に落ち、混ざり合うことなく流れていく。
眼前に直接突きつけられるよりも恥ずかしく、夏目は身をよじった。
その弾みで口腔を犯していた指を噛む。
「おっと。歯を立てるな」
斑は口から指を抜いて、人差し指の背に滲んだ血を夏目に見せ付けた。
「…あ…ごめん」

「お前も大概、お人よしだな。ここまでされて謝るとは」
斑は手を止めて、呆れたように言った。
「そうかも…しれない、けど」
「けど、なんだ?」
朱に染まった耳朶にわざと息を吹きかけるように、斑は夏目に尋ねた。
夏目の若い身体は、斑との交歓を喜んでいる。
こういう行為が好きなわけではないし、理性では拒んでもいるのだが、本能が許してくれない。
もとより夏目は斑のことを好いているのだ。求められることそのものは嬉しいのだ。
だから、拒みきれなかった以上、今の状況は合意であり、その相手に傷をつけたくなどない。
ましてや、斑なのだ。
傷を負った姿など、もう二度と見たくない。
この思いをすらすらと口にできるほど、夏目は雄弁ではない。
口ごもった夏目の目を、斑は掌で覆って言った。
「こんな傷など、すぐに治る。それより、仕切りなおすとしようか」
斑は夏目を目隠ししたまま、反対の腕を胴に回して夏目をひょいと持ち上げた。
ゆらゆらと揺れる感覚で、どこかに運ばれているのが分かる。それはそう長い距離ではなかった。
目隠しを解かれると、そこは先ほどまで立ってた場所からほんの数メートルしか離れていなかった。
岸に近い、沼に向かって倒れるように張り出した大木の下だ。少し浅く、足の裏に砂の感触があった。
斑は後ろからぐいと夏目の身体を前に押した。
前かがみになった夏目は手を伸ばし、大木の枝に縋りつく。
木の葉の揺れる音が、夏目の耳にやけに響いた。
すると、斑が後から夏目を押さえ込むように、圧し掛かってきた。
「あそこでは少々やりにくい。お前もこのほうが楽だろう?」
斑はそう言いながら、夏目の後ろ髪を掻き分けて、首筋をねっとりと舐めた。
びくりと震えた身体を片腕で拘束して、下着をゆるゆると下げて、中の性器を取り出し刺激した。

少しは収まりかけていた火が、また燃え出した。
#5
シャツの釦を全部は外さず、一つ二つ残しているのは、制服を濡らさないための気遣いなのかもしれないが、
素肌を布が擦れるたびにかえってむずむずするようなもどかしい感覚を覚える。
荒い熱い息が、夏目の口から不規則に吐き出される。
どんどん高まっていく熱が、出口を求めて下肢に集まる。
それが限界を超えようとしたとき、不意に夏目の背中から斑が退いた。
「…せ…ん、せ…。どう…し…」
夏目の問いは最後まで言葉にならなかった。
身体をくの字に曲げて木の枝にすがり付いている夏目の突き出された尻に、絶頂寸前の中心を放り出した斑が、顔を寄せていた。
「――あ、ああ…」
生暖かいモノがそこを滑る。差し込まれ、唾液を流し込まれる。
極短い間に唾液でどろどろになったそこに、今度は硬いものが差し込まれた。
それが斑の指だと分かったときには、指は内部を好き勝手に動き回っていた。
斑には知り尽くした場所であるに違いない。
簡単に夏目の感じる場所にたどり着き、そこを指の腹で撫で擦る。
「ふ…っく…。せんせ、い…。も…やめ…」
枝に縋りつく腕にも力が入らない。震える声で訴える。
「そろそろ、よさそうか」
斑の指が、夏目の尻から離れる。
この後に来るものを夏目は知っている。
拒むことなど、できようはずもない。夏目は枝を掴む手に力を込めた。
「――んんっ…っあああああっ!」
熱い楔が、夏目の中に打ち込まれる。
どれだけ丹念に馴らされても、この辛さにだけは慣れそうにない。
必死で悲鳴を堪えても、飲み込みきれたためしはなかった。
斑の上体が、また夏目の背中に圧し掛かる。
「いつもより…キツイな。まだ、足りなかったか?」
夏目はぶんぶんと髪を振り乱して首を振った。
痛い、苦しい、辛い。でも、それだけじゃない。
「…い…から…、はやく…」
斑が息を呑んだのが、夏目にも伝わった。
そして、愛情深く、きつく抱きしめられる。
「手加減できると…思うなよ」
夏目の顎に手をかけて乱暴に後ろを向かせると、斑は激しく口付けた。
息も声も何もかも、全て斑に奪われる。
ようやく口腔が開放されたと思ったのもつかの間、斑は夏目の腰を強く掴み、狭い夏目の内部を抉った。
「――っふあっ…」
脳髄まで突き抜けるような快感が夏目を襲い、その刺激で下肢の熱が噴出した。
斑は言葉通り容赦せず、自身の高ぶりで夏目を貪った。
先ほどまでの手管を駆使した戯れではなく、まさに獣だ。
ギリギリまで抜き、最奥まで穿つ。
揺すられ、回され、擦られる。
「…んっ、ああっ…う、ぅあっ…」
一度放出したはずの夏目の性器は、すぐに硬度を取り戻した。
がまんなど効かず、はしたなく先端からどろどろした熱い液体が飛び散る。
しがみ付いている枝が、斑の揺さぶりにあわせて揺れて、緑の葉がガサガサと嵐のような音を立てる。
穏やかだった水面が、大きな波を作る。
「夏目、なつめ」
繰り返し夏目を呼ぶ斑の声に、答える余裕などない。
夏目の全身が、斑によって溶かされていた。
自分がいつ極まって、斑がいつ自身を解き放ったのか、夏目にはわからなかった。
「…おい、しっかりしろ、夏目」
気がつけば、夏目は枝にしがみ付いたまま、ぐったりと身体を倒していた。
背後にはまだ斑がいる。
「…あれ?…おれ…」
「意識を飛ばしておったようだな。これしきのことで気絶するとは、まったく非力なやつだ」
達したからか、夏目には正常な思考が戻ってきた。今まで自分がここで何をしていたかを思い出し、赤面する。
「今更顔を赤くなどするな。…まさか、一回こっきりで終われるなどと思ってはおらんだろうな?」
斑の猛りを突きこまれたままの尻を軽く揺すられ、夏目はぐっと息を飲み込んだ。
その時。
「おーい、ナツメさまー。どこですかーい?」
知らない声が遠くから夏目を呼んだ。
誰かが、この近くにいる。
「うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ!」
夏目は瞠目し、振り返りざまに背後の斑を力いっぱい殴った。
思いもよらない突然の夏目の反撃をよけられようはずもなく、斑の身体は夏目から離れ、ぶくぶくと水の中に沈んでいった。
「おかしいなぁ…。こっちから声がしたと思ったんすけど…。おーい、ナツメさまやーい」
声はどんどん近くなる。
下着をあげてシャツの釦をはめようとするが、動揺のあまり早くはできない。それでも、どうにかこうにか下着を上げて釦ははめた。
「えっと、あ、ズボン!ズボンはかなきゃ!ど、どこに…。あっ!岸だ!]
夏目は沼の岸に沿ってそろそろと移動しようとした。
ところが、その夏目の前に、ぬっと水の中から顔が出てきた。
「うわぁっ!」
「あ、やっぱりナツメさま、いた!」
嬉しそうな顔は緑色で、頭に皿もついている。
河童だ。
ズボンを脱いだ夏目を見ても変に思わないのは、妖だからだろう。こういうずれたところは、ありがたい。
「さっき、あの白い饅頭の妖と一緒にこっちに来るのが見えたんで――」
「誰が白い饅頭だっ!」
「うわおっう!白饅頭、何すんだ!」
白い饅頭が、水の中から飛び出してきて、河童に体当たりする。
もちろん本当の饅頭ではなくニャンコ先生だ。
片目の周りが赤いのは、先ほどの夏目の拳が当たったからだ。
「いいところで邪魔をしおって!せっかく巧いことやって二回目に――もげぼっ!」
赤い顔をした夏目がニャンコ先生の頭を押さえて水の中に押し込んで、黙らせる。
「ええっと…で、何のようだ?」
「いえね、ちょうどさっき、いいものが手に入ったんで、せっかくだから一緒に食べようかと…」
そう言って河童が水の中から取り出したのは、スイカだった。
ニャンコ先生が泳いでスイカに近づき、猫が毛糸玉にじゃれ突くようにスイカにまとわりついた。
「うおー!スイカだ、スイカ!河童、お前気が利くじゃないかー!スイカ!スイカ!食わせろスイカ!」
「
あ、それ、俺が落とした…」
あ、それ、俺が落とした…」
そういえば、元々は塔子に頼まれたスイカを取りに行って帰る途中で、スイカを落として、それを探しに来たのだった。
ここでどのくらいの時間を過ごしたのだろう。帰りが遅いと塔子が心配する。夏目の顔が青くなった。
「わ、悪い。それは俺が落としたスイカなんだ!今度礼はするから、今はそれを返してくれ!」
「ああ、そうなんすか。こんなところにスイカなんて、珍しいとは思ったんすよ。そういうことなら、さ、どうぞどうぞ」
河童は快く夏目にスイカを渡してくれた。
「ありがとう。すまない」
夏目は河童に礼を言って、夏目は片手にスイカ、片手にニャンコ先生を抱えて、岸へと向かう。抱えられたニャンコ先生がじたばた騒ぐ。
「夏目!さっさと帰って食うぞ!スイカー!スイカーっ!」
「馬鹿、これは帰って塔子さんに渡すんだから。ほら、帰るぞ。ごめん、急ぐから!」
河童の見送りを受けて大急ぎで岸に上がり、ズボンを履く夏目の肩にニャンコ先生が飛び乗った。
「こら、急ぐんだから――」
「早く帰るぞ。スイカの前にお前を食わねばな」
ニャンコとは思えない、甘さを含んだ低い声で囁かれ、片足をズボンに突っ込んでいた夏目は、バランスを崩してその場に転んでしまったのだった。
その後。
スイカの前に夏目が頂かれることはなかった。
夏目の懸念通り、帰りの遅い夏目を心配した塔子が玄関で待っていたのだ。
さすがのニャンコ先生も塔子には弱い。
夏目の懸念通り、帰りの遅い夏目を心配した塔子が玄関で待っていたのだ。
さすがのニャンコ先生も塔子には弱い。
だが、皆が寝静まってから夜這をかけてきた斑を拒みきれなかったのは、斑の言うように
「あんな性急な一回きりで、お前だって足りるわけがない」
からではなく、急に来た夏の所為だと、夏目は思うことにした。
でなければ、恥ずかしくて耐えられそうにない。
終わり。